一人娘だった。
そして、その娘は虚弱体質だった。
日常生活に支障はないものの、ただの風邪が肺炎に悪化する、なんてことはしょっちゅう。
両親が過保護になるのも仕方がないと言わざるを得ない。
それはそうだ、まぁ仕方がない、と多くの人間が思っている。
そして、その過保護な親が、金持ちであればなおさらそうだろう、とも思っている。
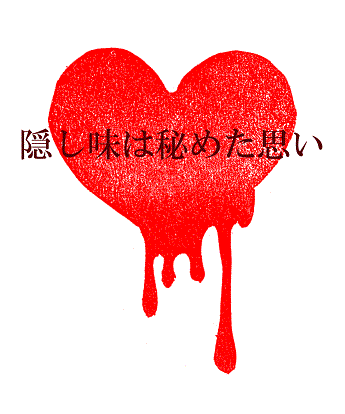
ゆっくりと開いた瞳。ぼやけた視界が見慣れた白い天井を捉えた瞬間、意識は一気に覚醒し、は自分を殴りつけたい衝動に駆られた。
またやってしまった―――――。
自分自身に対する怒りで詰まりそうな胸を押さえながら、ムクリと起き上がる。目眩はしなかった。大丈夫だろうと判断し、ベッドの脇に揃えられたスニーカーに足を通す。
カーテンを開けると、が起き出すのを気配で察していたらしい校医が微笑んで出迎えてくれた。
「気分はどう?」
「大丈夫です」
「最悪です」という本音は飲み込まざるを得ない。
ぎごちなく笑みを浮かべながら答えるに、校医は回転椅子から腰を上げた。
日本人らしい擦り足で、音を立てずに近付くと、
「今日は階段の踊り場で倒れたんですって。貧血が原因かしら。踊り場だったのが、不幸中の幸いね。落ちなくて良かったわ」
困ったように眉を下げて微笑みながら、校医はの顔に手を宛て、ジッと見詰める。目の下の皮膚を引っ張り、粘膜の状態を確かめながら、「まぁ、大丈夫かしらね」と頷く。
「あの、先生―――――」
されるがままになりながら、意を決して口を開いたに、校医はますます困ったような顔になった。
彼女のその顔に、ほぼ答えをもらったようなものだと思ったが、それでもは尋ねずにはいられなかった。
そして、それは校医も同じだったらしく、が質問を口にする前に、
「ごめんなさいね、さん。あなたが嫌がるのは解っていたんだけど、鳳くんには知らせてもらったわ」
白衣のポケットに片手を突っ込みながら答えた。
その答えに、解っていながらも胸がつかえた。どうして私は、いつもこうなんだろう。
「部活を切り上げてくるそうよ。知らせたのが15分前だから、そろそろ来るんじゃないかしら」
申し訳なさそうにまつげを伏せる校医の姿に、ますます胸が痛んだ。
彼女だって、こんな気不味い思いはしたくないに違いない。
けれど、そうせざるを得ない――――何せ、彼女の父親はの母親の生家が営む製薬会社に勤めているのだから。
誰に言われた訳でもないが、彼女が校医になったのもおそらく母の差し金だろうとは思っている。校医は白衣姿がよく似合っているが、それは医療関係者というよりも、研究者然としていた。校医の資格保持者を会社関係者内から探したのか、命令して資格を取らせたのか。どちらかは判らないが、体の弱いの保護を目的としているのは明らかだった。
自分の息の掛かった人間を娘の学校の校医にすることなど、跡部や榊に及ばぬとも多額の寄付金を納めるにはたやすかったに違いない。跡部や榊に比べ、は医療業界に限れば群を抜いている。
そう、そして―――――
「すみません、遅くなりました」
可能な限り音をたてずに、という気遣いが感じられる所作で開かれた保健室のドアの向こうに、背の高いシルエットを捉えた瞬間、は無性に泣きたくなった。
「――――ああ、ちゃん。気が付いたんだね?良かった」
ドアをゆっくりと開き、の顔を確認すると、心底嬉しそうに微笑んだ。
その後、直ぐに笑顔が「大丈夫かい?」と心配そうな顔をに変わる。
慌てて結んだのか、いつもキッチリ締まっているネクタイの結び目が緩い。
彼の顔を見ているのが居たたまれなくて、下げた視線の先にも、自分の為に彼が貴重な練習時間を割いてくれているという事実を思い知らされる痕跡を見付けてしまう。
自己嫌悪なんて生易しいものじゃすまされない。この衝動を言葉にするのは難しくて出来ないが、無理にでも言語化するのであればこれが近いだろうと、は思う。
―――――死にたい。
自分が泣くのは狡い上にお門違いだと、解っているからこそ、溢れそうになる涙を押さえるのに苦労を要した。
声が震えぬよう、チリチリと熱い喉を唾液で十分に濡らしてから言葉を発する。
「ごめんなさい、長太郎くん―――――」
鳳長太郎。彼の父親は総合病院の顧問弁護士をしている。
病院は裁判に事欠かない。顧問料以外にも、便宜に応じた弁護料を潤沢に支払う、弁護士にとっては最高の顧客だろう。
パワーバランスははっきりしている。そんな状況で、の父親は鳳長太郎にこう言い放ったのだ。
「中学から、は氷帝学園に入学することになったんだ。長太郎くんと学年はひとつ違うけれど、良くしてやってくれるかい?何せ、この子は体が弱くて直ぐ倒れるからね。私たちは心配なんだ」
社会的権力に裏付けされた言霊の威力は絶大であった。
の入学以来、鳳は彼女が体調を崩す度、送り迎えを担っている。
判り切っていたことだったが、「体調は戻ったから一人でも帰れる」と言うの意見は校医と鳳によって却下された。
「さん。あなた、今月だけで保健室にもう5回来てるのよ?」
噛んで含めるように諭され、結局鳳と岐路を共にすることになった。
車を呼べば事足りることだというのに、の父親は車通学を許さなかった。これは、彼が姉を車通学中の交通事故で亡くしていることに由来しており、絶対のルールであった。
車通学という手段が使えないが故に、白羽の矢を立てられたのが、家が近所で同じ学校に通う息子を持つ鳳家であった。
榊や跡部に比べ、は防衛業に関しては秀でていない。お抱えのボディガードなどいないのだ。わざわざ雇うのも、自分の息が掛かっていない者を使うことに懐疑的な母が却下したに違いない。
そんな中で、鳳家の存在は丁度よかったに違いないと、は思う。自分の病院の顧問弁護士という立場所上、自分の願いを無碍に断られることはないという父親の打算もあっただろう。
その目論見は見事に的中し、鳳家の息子はの面倒をしっかりと看ている。
最初の1、2ヶ月は「申し訳ない」という後ろめたさで心が重いだけだった。鳳を目の前にすると萎縮してしまい、鳳も鳳でに対して恐縮しており、お互いに居心地の悪い空気に困惑していたものだ。
しかし、しばらく一緒に時を過ごすうち、鳳の真摯で真面目な、それでいて底無しに他者に優しい人柄に触れ、の胸の重みは肥大し、痛みを伴いだした。
膿んだ傷口のようにジクジクした痛みがもたらす苦しみに、夜な夜な一人で涙を流して耐え続け、ようやくは己の恋心に気付いた。
長太郎くんのことが、好きだ―――――。
気付いてしまえば単純明快で、それでいて肩に酷く重くのしかかる、頭の痛い事実であった。
これだけ負担を強いているという現状を前にして、どの口が好きだと言えよう。
それに、権力を用いて圧している相手から好意を伝えられたところで、それを断ることが出来るものだろうか?―――自分だったら、とても出来ない。ならきっと、彼も同じだろう。
そう思えば、貝のように押し黙る以外、に選択肢はなかった。
鳳が世話を焼いてくれることに対して、クラスメイトの女の子たちは「ちゃん、いいなぁ。鳳先輩って素敵だもんねぇ」とを羨ましがったが、はクラスメイトたちが羨ましくて仕方がなかった。
何のしがらみもなく、鳳を素敵だと、好きだと言える。その状況が、喉から手が出る程欲しいものだった。
背が高く、柔和な顔立ちで、誰に対しても親切な上に、2年生にしてテニス部でレギュラーを努める。そんな鳳が女生徒の人気を集めない訳がない。
その鳳に世話を焼かれながらも、は一度も面と向かって鳳に好意を寄せる人間に怒られたことがない。
レギュラーである鳳の練習を中断させることに対して、跡部や榊といった、以上の権力保持者から咎められたこともない。
鳳自身、跡部にの世話焼きの為に練習を抜けることを怒られず、「行ってこい」と言われ、驚いたらしい。
社会的階級は劣っていても、生命を握る医療がフィールドであるという点で、は強かった。跡部も榊も、重役の年長者は病院で面倒を看ている。お互いにないがしろに出来ない、厄介な間柄なのだろう。
せめて誰か、面と向かって叱ってくれればいいのに。
は長らくそう思っている。そして、それが叶わぬ願いらしいと気付いてもいる。
――――否、一人だけ居る。
そう、一人だけ。この願いを叶えられるのは、鳳本人以外にあり得ないだろう。
彼自身が、以上に大切な存在を見付けた時。
思い至った答えに、ジクジクと胸の痛みが疼く。
現状を打破したいのに、自分ではそれが出来ない。鳳が動くのを待つしかない。
傍に居てもらうにしても、離れるにしても、それは変わらない。こちらから動けば彼に圧力を与えてしまい、本音を飲み込ませる結果になってしまうだろう。
長太郎くんの彼女さんって、どんな人がなるんだろう。
Mッ気はないと思っていたが、間違っていたらしい。自分に対していやに加虐な思考にうんざりする。自ら苦しくなる道を選んでどうするつもりなんだろう?
それでも思考は止まってくれない。
宍戸先輩みたいな人かな。
鳳が憧れる先輩。サバサバとした気持ちの良い人で、の体調不良で二人の練習が中断されてしまっても、一度も文句を言われたことがない。「おう、気を付けて帰れ」、いつもそう言う。体調はどうだとか、大丈夫かとか、そういうことは一切言わない。それが宍戸流の優しさらしいと気付いたのは、しょっちゅう鳳の口にあがる「宍戸先輩情報」からだ。
ああいう性格の人が長太郎くんの彼女さんだったら、きっと「私はいいから、送っていってあげて」って、優しく微笑むような人なんだろうな。――――そうしてきっと、私はますます居たたまれなくなるんだ。
「気持ち悪くなったら、すぐ言ってね」
穏やかに微笑む鳳に頷いて見せ、校医にお礼を言う。
白衣のポケットに片手を突っ込んだ校医に「気を付けて帰るのよ」と見送られ、とぼとぼと、亀のような歩みで保健室を後にする。
ふと、に歩調を合わせ、ゆっくりと進む鳳の荷物が平素より多いことに気付き、はじっとそれを見詰めた。
小さな、ピンク色の紙袋。
学校指定の鞄と、テニスバック。いつものようにそれを担ぐ鳳の右肩の先。
右手に握られた紙袋に、視線を注ぐ。
他意はなかった。いつもと違うから気になっただけだった。けれど、自分で思うよりも熱心に見ているように感じられたらしい。
の視線に気付いた鳳が、「ああ、これ?」と軽く右手を上げる。
その言葉に、視線を紙袋から鳳へと上げると、彼は困ったような顔をしていた。
「えぇと」と口ごもり、迷うように唸る。
「――――ちょっと早いけど、バレンタインデーのチョコレートをもらったんだ」
その言葉に、確かにちょっと早いな、とは思う。そして、賢いな、とも思う。
今日は2日。バレンタインデーはまだ先だ。けれど、今渡しておけば、バレンタインデー当日に渡すよりも確実に彼に食べてもらえるだろう。それに鳳の場合、チョコレートは先に渡し、14日当日には食べ物でないバースディプレゼントを渡せば良いのだ。
バレンタインデーを思い、の思考の闇が深まる。
鳳に渡すつもりで、練習を重ねたチョコレートブラウニー。
・・・・やっぱり、どこかお店で買おう。そうしよう。
ふと、少し前に友人に借りた少女マンガの主人公を思い出す。彼女は好きな男の子に、手作りのチョコレートを渡すことが出来なかった。その理由は、自分の下心の入ったチョコレートを渡すことを恥じたからだった。
主人公の気持ちが良く解る、とは思った。下心たっぷりの、手作りのお菓子。そんなおどろおどろしいものを、爽やかな鳳にあげようとしていたなんて、何て自分は恥知らずなんだろう。
「姉さんに、長太郎はちゃんの手作りチョコレートがもらえるからいいわねって羨ましがられたよ」
「―――――え?」
言われた言葉の意味が判らず、キョトンとするに、鳳はにこやかな笑顔を向けながら続ける。
「ほら、姉さんの誕生日に、ちゃんが手作りのチーズケーキを焼いてくれたでしょ?あれ、すごく美味しかったから、ちゃんの手作りチョコレートもすごく美味しいに違いないって姉さんが。・・・俺もそう思うよ」
「・・・・・」
「楽しみにしてる、って言ったら、ちゃんの負担になっちゃうかな?」
苦笑する鳳の言葉に、視界が滲む。
堪えきれずに溢れ、ポタポタと落ちる涙に鳳がギョッとした。
「――――どうしたの?気持ち悪いのがぶり返しちゃった?」
どうしてそんなに底無しに優しいのか。
あなたを好きでいることすら諦めさせてくれないだなんてそれどころかますます好きにさせるだなんて。
そんな優しいところが、好きだけど嫌いだ。
矛盾する感情は膨れ上がるばかりで、涙腺をますます刺激する。オロオロする鳳を前に、頭の片隅でチョコレートのことを考える自分のことを、嫌らしいと思った。
けれど、隠し味は、下心入りのチョコレートブラウニーのことを考える自分からは、どうしようもなく、「女の子」が溢れているとも思った。